- まちづくり・地域活性課題
- Focus
2025.02.19
御堂筋将来ビジョンの実現へ 新たな賑わい創出に挑戦!
人とモビリティの共存空間をめざした
官民連携でのまちづくり実証実験
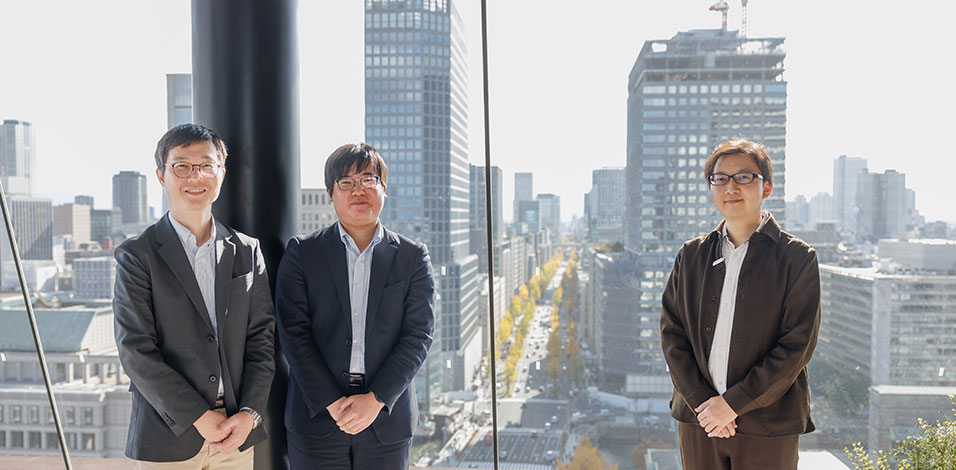
大阪市の中心部は大きく「キタ」と「ミナミ」に分けられます。キタの玄関口である梅田と、ミナミの玄関口である難波まで、約4.2kmを直線で結ぶ大阪のメインストリート・御堂筋。都市機能が集約し無類のポテンシャルを秘めた御堂筋を、さらに飛躍させるための大型プロジェクトが進行しています。キーワードは、車中心から人中心のストリートへ。JTBコミュニケーションデザイン(以下、JCD)は大阪市から委託を受け、2019年に策定された「御堂筋将来ビジョン」に基づく空間再編を、大阪市建設局様や地元の人々と協議しながらブラッシュアップしています。大阪・関西万博時にはサテライト会場としての大型イベントも実施予定。御堂筋というまちの変革に立ち会う空間再編プロジェクトについて、大阪市建設局で道路空間再編担当の中西祥人氏、吉田耕平氏と、JCDの杉田大輔に話を伺いました。
※本事業は大日本印刷株式会社とパートナーシップを組み、共同企業体として受注しています。
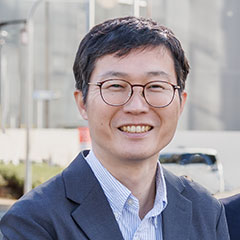 大阪市 建設局 企画部 企画課
大阪市 建設局 企画部 企画課
担当係長
中西 祥人 氏
 大阪市 建設局 企画部 企画課
大阪市 建設局 企画部 企画課
吉田 耕平 氏
 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
コーポレートソリューション部 プロモーション第二事業局
エグゼクティブプロデューサー
杉田 大輔
1 御堂筋をリブランディングする理由
――まずは御堂筋そのものについてご紹介いただけますか。
中西氏
現在の御堂筋が開通したのは1937年です。そこから長きにわたって大阪の発展を支えてきた、このまちの大動脈です。双方向通行から南行き一方通行となったのは前回の大阪万博が開催された1970年のことでした。高度成長期のマイカーブームによる混雑を避けるために行った対策でした。現在は、車道本線の両側には車が寄せやすいよう側道も設置され、冬のイルミネーションも楽しいイチョウ並木が御堂筋のシンボルとして親しまれています。

――「御堂筋将来ビジョン」策定の背景やリブランディングの必要性について、教えてください。
中西氏
実は1958年から御堂筋は国の管理となっていましたが、道路と周辺が一体となってまちづくりを進めるべく、2012年に再び大阪市に移管されました。建設当初と比べると、人の行動やまちの状況、交通環境も大きく変化しています。平成初期以降、少子高齢化などで都市部は空洞化、自動車交通量は年々減少傾向にあります。そこで、建設から80周年を迎えた2017年に地域の方々と交わした意見の取りまとめがあり、2019年3月に、車中心から人中心のみちへと空間再編をめざす今後の御堂筋のあり方や公民連携したまちづくりのあり方など、今後御堂筋がめざすべき姿を示した「御堂筋将来ビジョン」が策定されました。
――「御堂筋将来ビジョン」には、どんな未来が描かれているのでしょう。
中西氏
2037年の御堂筋完成100周年をターゲットイヤーに設定し、人中心の都市空間をめざしています。限りある都市空間をより有効的に使うためにはどうすればいいのか。パブリックスペースの心地よさをどう作り出すべきなのか。より良い都市空間のあり方について、今後も検討は続いていきます。側道を歩行者空間に変える取り組み、社会実験などを行う事業は、将来ビジョンへとつながるファーストステップです。
2 「御堂筋チャレンジ2024」で未来を想像
――昨年9月に実施された「御堂筋チャレンジ2024」、「御堂筋サテライトプレ社会実験」も、「御堂筋将来ビジョン」と関連があるのでしょうか。
吉田氏
御堂筋では、2017年から「御堂筋チャレンジ」という名を掲げて官民連携によるストリート運営の仕組みづくりを探求しています。JCDさんにご協力いただいた2024年9月の「御堂筋チャレンジ」、「御堂筋サテライトプレ社会実験」は大阪・関西万博の半年前のタイミングでした。翌年の大阪・関西万博開催の際、御堂筋をサテライト会場として活用する予定ですので、そこを強く意識しました。具体的には、淀屋橋交差点から難波西口交差点の間で、側道の通行規制や本線の車線規制を実施。より、人中心の空間をイメージした将来の御堂筋を可視化する、という試みを実行しました。平時は車が通っている場所で行った街角コンサートやアーバンスポーツ、グランピングなどの新たな体験を、参加者がとても楽しんでくださりました。私たちも、道ゆく人も、将来の御堂筋の姿が垣間見えたことが、今回のチャレンジの収穫だと思います。
杉田
期間中は、交通規制をスムーズに行うため、吉田さんと私でカラーコーンを手に持って走る場面が何度もありましたね。これまでJCDは多種多様なイベントに携わってきましたが、大動脈を閉鎖して新しい空間を創造するといった試みは私にとっても初めての経験でした。イベント当日にすべきことはもちろん、そこに至るまでのプロセスにもかなり時間を費やしました。例えば、関係機関と協議するための資料を作るなど、1つずつクリアして本番を迎えました。今回のトライアンドエラーを活かし、来年のサテライト会場はもっといいものにしたいと考えています。本当にチャレンジングな事業にご協力させていただいていると感じています。

3 大阪・関西万博を御堂筋から盛り上げる
――2025年が本番となる大阪・関西万博のサテライト会場、どんなイベントが行われる予定ですか。
杉田
2024年も好評だったアーバンスポーツの幅を広げ、話題のパルクールを企画したり、移動図書館で子供たちに楽しんでもらおうとか、「御堂筋チャレンジ」協議会の皆さんからもすでに様々なアイデアが出ています。御堂筋はエリアによって個性がありターゲットも異なります。特性のあったコンテンツを揃えることがとても重要だと捉えています。
中西氏
御堂筋は、北側が主にビジネスエリア、真ん中が問屋街や住宅とビジネスの複合的なエリア、南側は賑やかな繁華街エリアと、ゾーンによって特性が違うんです。南側で人気のコンテンツを北側に導入しても、受け入れられないことがあります。歴史や景観はもちろん、地域の歩行者量やインバウンドの多い少ないなど、エリア特性をとらえた企画をすることが成功の鍵。JCDさんは特性をキャッチして、エリアにマッチするご提案をしてくださると感じています。
――サテライト会場でイベントが実施されるのは、いつですか?
杉田
大阪・関西万博の会場内で大阪の魅力を国内外に発信する「大阪ウィーク」と同時期です。5・7・9月にそれぞれ約10日間ほど実施される予定になっています。御堂筋に設けるサテライト会場では、5月はアート、7月はサマーキャンプと題したお祭り、9月は未来の御堂筋を彷彿させるウォーキングのイベントを企画。
特にフィナーレに近づくウォーキングでは、約4.4kmを歩きながら御堂筋の魅力を再発見してもらい、御堂筋の未来を想像できるイベントにしたいと思っています。私自身、御堂筋の移動は極力歩くことにしているんです。自分が歩く速度で見て、気づいた魅力がたくさんある。それを府民、市民だけでなく、大阪以外から来る方々にも体験していただきたいです。
中西氏
御堂筋のイルミネーションは通常11・12月だけの点灯なのですが、大阪・関西万博開催時は半年間実施すると聞いています。暑い時間は避け、日没後に夕涼みがてら歩いていただくのもイベント感があって楽しいと思います。
4 モビリティ活用ですべての人に快適を
――多様なモビリティが安全に共存する空間、というワードが御堂筋将来ビジョンに記されていますが、サテライト会場でも展開しますか?
中西氏
より人中心の空間が広がっていき、自動車が少なくなると、これからの人の移動をどうしていくか、ということも、一緒に考えていく必要もあります。それを解くカギとして2024年も試した、新たなモビリティの実証実験が不可欠だと考えています。人が乗るモビリティだけじゃなく、荷物を目的地に運搬するとか、販売商品を輸送するとか、いろんな役割を想定しています。
吉田氏
2024年のプレ社会実験では、ベンチ型モビリティを導入しました。これは、3人が並んで腰掛けられる設計で、歩道上を移動するものです。また、車椅子の代替となる1人乗りのモビリティも用意し、来場者の皆様にご利用いただきました。座って移動することで、普段とは異なる視点から街を見ることができ、新たな発見につながったようです。「イチョウの様子をゆっくり観察できた」や「適切に整備された景観に改めて気づいた」などの感想が寄せられました。
中西氏
御堂筋の将来像に関して、個人的に思い続けているキーワードが2つあります。ひとつはすべての人を包むこむ空間でありたいというインクルーシブ、もうひとつがコ・クリエーション。いろんな立場の人たちと対話しながら新しい価値を生み出していきたい、そう思っています。

5 御堂筋を企業のPR活動の場に
――これからの御堂筋には、都市空間を利活用していくアイテムが増えていきそうです。
中西氏
利活用するための設えを整備していくことで、「御堂筋の未来を見たい」という企業様にアピールできるのではないかと考えています。2025年の「御堂筋チャレンジ」でもハンギングバスケットやバナー広告などを検討しています。
ぜひ、多くの企業に御堂筋の未来に期待や興味を持っていただき、これからもバナー広告の認知度をあげ、新店オープンの販促ツールとしてジャックしていただくなど、企業のPR活動の場としての御堂筋を一緒になってPRしていきたいですね。
――新たなPRの場、スタートアップ企業の育成にも活用できそうな気がします。
中西氏
今はまだどうなるかわかりませんが、個人的にはぜひ取り組みたい事業の1つです。スタートアップ企業やベンチャー企業が御堂筋を媒介にして収益性を高めてもらい、御堂筋の活気にもつなげていく。例えば、これまで決まった会場で行っていたモビリティショーや展示会などのイベントを御堂筋で繰り広げれば大きな話題となるでしょう。デジタルサイネージやプロジェクションマッピングなどに強いITテクノロジー系の企業とも相性がいいかもしれません。
――その他、既に御堂筋将来ビジョンに共感をいただいて、協賛いただいている企業様などいらっしゃるのでしょうか。
吉田氏
御堂筋という比類のない大阪のストリートに、地元の皆さんはとても愛着をもっていらっしゃいます。特に街路樹のイチョウへの思いは強く、樹勢が弱ったイチョウは市内の公園などに移植して再生を試みています。「イチョウを大切にしたい」という地元の人のやさしさや、サステナブルな活動に賛同し、イチョウ並木に対して継続支援をしてくださっている企業もありますよ。

――2037年に100周年を迎える御堂筋に対して、今どんな思いを抱いていますか。
吉田氏
人中心の空間を目指すことを掲げていますので、そういう未来に期待しています。とは言いつつ、一方で、エリアごとの特性に対してどんな形の利活用が一番いいのか、みんなで考え、修正を重ねることが最も大事なことです。ビジョンは、今後御堂筋がめざすべき姿を表したものであり、取組みの方向性を示したものです。100周年は、議論の先に見えてくる快適な空間をみなさんと探求していきたいと思っています。
中西氏
2037年を見据えたプロジェクトを検討する際、カーボンニュートラルへの配慮は必須です。すでに御堂筋エリアは脱炭素先行地域に選定されていることもあり、2030年度までに官民一体で御堂筋エリアの電力消費に伴うCO2排出実質ゼロに取り組んでいます。ウォーキングプログラムにグリーントランスフォーメーション(GX)、床発電や太陽光、振動発電といった、未来の電力を取り入れるといった意見も協議会などですでに出ています。活動に共感してくださる企業を募り共に開発し、御堂筋将来ビジョンの実現に近づいていきたいです。
杉田
当社の事業委託は2024・25年の2年間ですが、それで終わることなく、御堂筋のプロジェクトに寄り添っていきたいと、強く思っています。この事業担当になった当初は万博関連の事業だな、という理解でしたが、もっと前からビジョンは進んでいましたし、万博よりもっと先にもビジョンが描かれていることを知り考えが変わりました。もし、このビジョンに共感いただける方がいらっしゃり、御堂筋での新たなプロジェクトにご興味お持ちの企業や自治体がございましたら、ぜひお問い合わせください。

以下より、関連資料をダウンロードいただけます。









